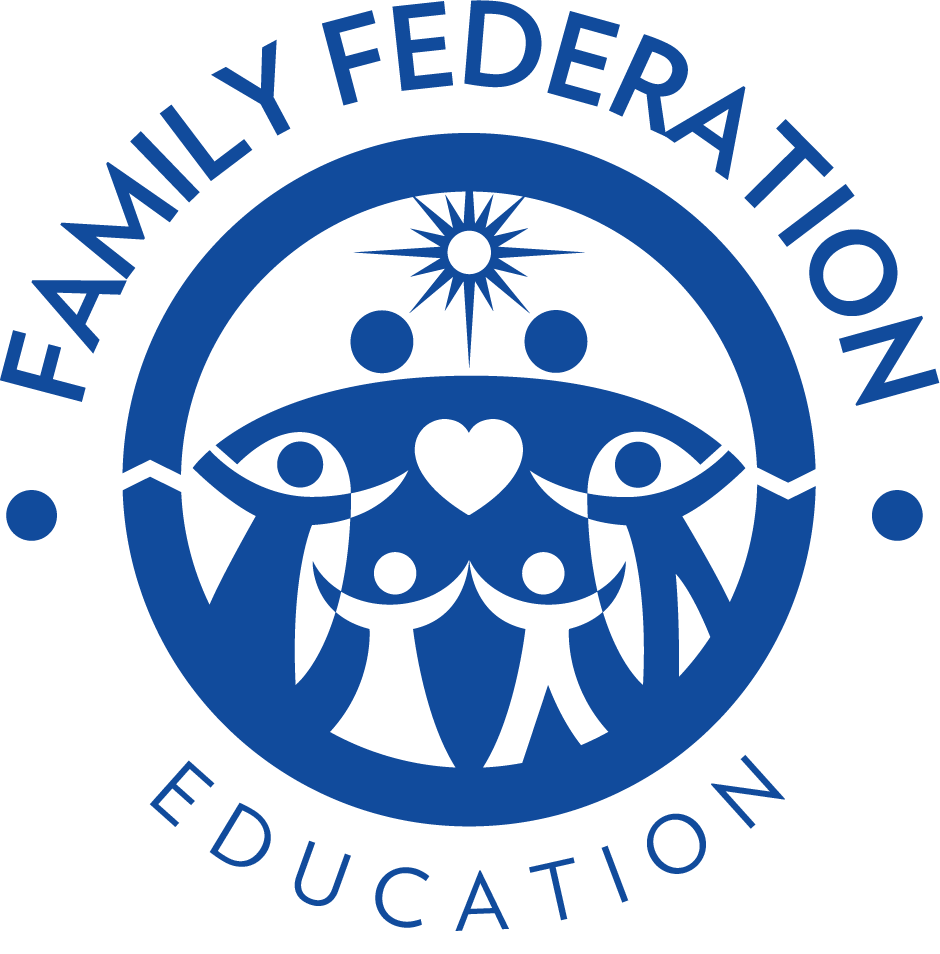平和を愛する世界人として 第19話
ご飯粒一つが地球よりも大きい
平壌刑務所に入所して一カ月半が過ぎた五月二十日、私は興南監獄に移送されました。自分一人であれば逃亡でも何でもできましたが、強盗犯や殺人犯と一緒の組になっていたので、できませんでした。列車で十七時間ほどかかる遠い道のりを行きながら、じっと座って窓の外の光景を眺めていると、悲しみが込み上げてきました。脇を小川の水が流れ、うねうねと谷間に続くその道を、囚人の身となって行かなければならないのです。開いた口がふさがらないとはこのことでした。
興南監獄とは、興南窒素肥料工場の特別労務者収容所のことです。そこで私は二年五ヵ月の間、苦しい強制労働に従事しました。強制労働はもともとソ連で始まったものです。ソ連は、世論と世界の目があるために、資本家や反共主義者をむやみに抹殺するわけにはいかず、新たにこの刑罰を考案しました。強制労働の刑を受けると、つらい労働にへとへとになりながら死ぬまで働くしかありません。この制度をそのまま真似た北朝鮮の共産党は、すべての囚人に強制労働をさせました。過酷な労働をくたくたになるまでやらせて、自然と死ぬように仕向けたのです。
興南監獄の一日は明け方四時半に始まります。囚人を全員起こして前庭に整列させ、不法な所持品がないかどうか、まず身体検査をします。衣類を全部脱がして、埃一つも見落とさないようにパタパタ叩いて隈無く探すので、優に二時間はかかりました。興南は海が近く、冬には脱いだ体に寒風が吹きつけて、肉が抉られるような痛みがありました。身体検査が終わると、粗末な朝ご飯を食べ、十里 (約四キロメートル) の道を歩いて工場に向かいます。四列に並んで、顔を下に向けたまま、手をつないで歩きます。囚人たちの周りを小銃と拳銃で武装した警備員たちが付いて行きました。万一列が乱れたり、手が離れたりすると、脱走の意図ありとみなされ、容赦なく殴打されました。
雪が道に積もった冬の日、寒い明け方の道を歩いていくと、頭がくらくらしました。凍りついた道はよく滑るし、肌に突き刺さるような冷たい風が吹くと、頭の後ろの毛が逆立ちます。朝ご飯を食べたといっても、元気は出ません。足を踏み外してばかりいる毎日でした。しかし、力の抜けた足を引きずってでも工場に行かなければなりません。道すがら意識が朦朧となる中で、私は自分が天の人だという事実を繰り返し考えながら歩いて行きました。
肥料工場には、肥料の原料となる硫酸アンモニウム(硫安)が山となって積まれていました。ベルトコンベヤーで運ばれてきて、そこから下に降り注ぐ硫安は、白い滝のようにも見えました。降り注いだばかりの硫安は熱を帯びて、真冬にも湯気がゆらゆらと立ち上るほどでしたが、時間が緻つと冷めて氷のようにかちかちになりました。山と積まれた硫安をすくい上げて、かます(わらむしろを二つ折りにして縁をとじ、袋にしたもの)に入れるのが私たち囚人の仕事でした。「肥料山」高さ二十メートルを超える巨大な硫安の山の呼び名です。八百人から九百人が大きな広場に出て、硫安をすくい上げて袋詰めする場面は、あたかも大きな山を二つに分けるかのようでした。
十人一組で一日に千三百かますやるのが私たちに与えられたノルマです。一人の一日当たり責任量は百三十かますになります。それをやらないと食事の配給が半分に減らされてしまうので、生死の分かれ目と思って必死に働きました。硫安を詰めたかますを少しでも楽に運ぼうと、針金で輪を作って、かますを結ぶ際に使いました。運搬用のトロッコ(貨車)が通るレールの上にこの太い針金を乗せておくと、平らに潰れて針の代わりに使えます。かますに穴を開ける時は、工場のガラス窓を破って、そのガラスを使いました。看守も苦しい労働に悩まされる囚人に同情して、工場の窓を破るのを見てもそのままにしていました。私はある時、その太い針金を歯で噛み切ろうとして、そのまま歯が真っ二つに折れてしまいました。今でも私の門歯をよく見れば歯が欠けていますが、興南監獄で得た忘れることのできない記念品です。
どの囚人も重労働で疲労困態して痩せこけていくのに、私は体重七十ニキロをずっと維持して、囚人たちの羨望の的でした。体力だけは維持して少しも他人が羨ましくなかった私も、一度だけマラリアにかかってとても大変だったことがあります。一月近くマラリアにかかっていても、私が仕事をできなければ他の囚人たちが私の分までやらなければなりません。そうならないように、一日たりとも休みませんでした。このように体力があったので、私は「鉄筋のような男」と呼ばれました。いくらつらい重労働であっても我慢できました。監獄であろうと強制労働であろうと、この程度は問題になりません。どんなに鞭が恐ろしく、環境が悲惨だとしても、心に確固たる志があれば動揺しませんでした。
日本の川崎鉄工所で働いた時、タンクに入っていって硫酸を清掃しましたが、毒性のために死んだ人を数人目にしました。しかし、興南工場は、それとは比較にならないくらいひどい所でした。硫酸は有害で、触れると髪の毛が抜け、皮膚から粘液が流れます。硫安工場で六カ月も働けば、喀血して死ぬ人もいます。指を保護しようと指貫をはめても、かますを結んでいると、有毒な硫安に触れてすぐに穴が空いてしまいました。着ていた衣服は硫安で溶けて擦り切れてしまい、肉がひび割れて血が流れるか、骨が露わになる場合もありました。肉が削げ落ちたところから血がどろどろと流れ、粘液がだらだら出てきても、一日たりとも休まずに仕事をしなければなりませんでした。
それだけ仕事をしても、ご飯は一日に小さな茶碗で二杯にならない配給しかありません。おかずはほとんどなく、スープは大根の葉の入った塩水がすべてでした。スープはちょっと口にしただけでも塩辛かったのですが、石のようにごつごつしたおかずなしのご飯はそのままではのみ込めないので、そのような塩辛いスープでさえも貴重で、誰一人としてスープの汁を無駄にする者はいませんでした。
ご飯茶碗を受け取ると、どの囚人も一瞬にして丸ごと口の中に入れます。自分の分を食べ終わると、他の人がご飯を食べる姿を、喉を鳴らして眺めています。ある時は、我知らず人のご飯茶碗にスプーンを突っ込んで、争いが起きることもありました。同囚のある牧師は、「豆一粒だけくれたら外に出てから牛二頭あげる」と言ったほどです。死人の口の中に残ったご飯粒まで取り出して食べるほどでした。興南工場で味わった空腹は、それほどまでに凄絶でした。
空腹がもたらす苦痛は、実際に味わってみなければ分かるものではありません。空腹が極まったときは、ご飯粒一つでもどれだけ貴いかしれません。今も興南のことを思うだけで気持ちがさっと引き締まります。ご飯粒一つがそこまで人間の全神経を刺激できるということが信じられませんでした。おなかが空けば涙が出るほどご飯が恋しくなり、母親よりもっと恋しくなります。おなかがいっぱいのときは世界の方が大きいのですが、おなかが減ればご飯粒一つが地球よりもっと大きいのです。ご飯粒一つの価値とは、そのように驚くべきものです。
興南監獄では、配給された握り飯の半分を同僚たちに与え、残りの半分だけを食べました。約三週間そうやって実践した後、初めて握り飯一つを全部食べました。二人分のご飯を食べたと考えれば、空腹に耐えることがとても楽になります。
興南の実態は残酷の一語に尽き、実際に体験したことのない人には想像すらできないでしょう。囚人の半数が一年以内に死んでいきます。死体を入れた棺桶が毎日のように監獄の裏門に運ばれていくのを見つめなければなりませんでした。全身のあぶらが一滴残らずなくなるような仕事ばかりさせられて、死んで初めて門の外に出ていくことができたのです。いくら無慈悲で冷酷な政権であっても、それは明らかに人間としての限界線を越えたものでした。そのように囚人の涙と怨念がこもった硫安入りのかますは、港からソ連に運ばれていきました。