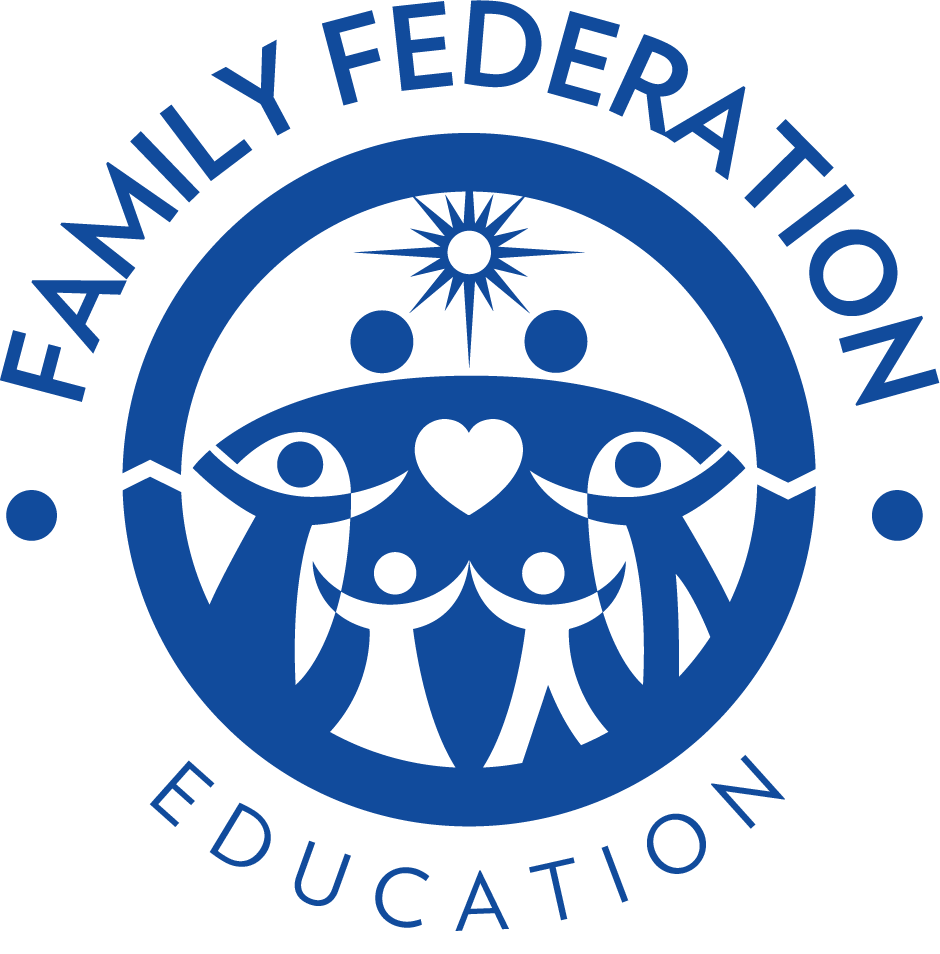平和を愛する世界人として 第18話
拒否できない命令
光復の直後、韓国の実情は言うに言えない混乱状態でした。お金があっても、米を手に入れることは簡単ではありませんでした。とうとう家に米がなくなったので、買っておいた米を取リに黄海道の白川に向かいました。その途中でのことです。
「三八度線を越えて行きなさい!北の方にいる神様に仕える人々を取り戻しなさい!」という啓示が下りました。
私は即座に、三八度線を越えて平壌に向かいました。長男が生まれて二月しか経っていない時でした。今か今かと私を待つ妻が心配でしたが、家に戻る余裕はありませんでした。神のみ言は厳しいものです。み言を受けたら、従順に即応しなければなりません。創世記から黙示録まで数十回も線を引いて読み、ごま粒のようなメモ書きで真っ黒になったぼろぼろの『聖書』一冊だけを携えて、私は三八度線を越えて行きました。
その時はもう共産党から逃れようと、北から避難民が続々と南下してきていました。特に、共産党が宗教を迫害したので、多くのキリスト教徒が宗教の自由を求めて南側に下ってきました。宗教はアヘンだと言って、民衆に宗教を持たせないようにしたのが共産党です。そのような地に、私は天の召命を受けて向かったのです。牧師であれば嫌う共産党の支配する世界に、私は自分の足で歩いて入っていきました。
避難民が増えるや、北側の警戒が物々しくなって、三八度線を超えることすら容易ではありませんでした。しかし、百二十里 (約四十八キロメートル) の道を歩いて三八度線を越え、さらに平壌に到着する時まで、なぜこの険難な道を行かなければならないかと私は一度たりとも疑いませんでした。
一九四六年六月六日、平壌に到着しました。もともと平壌は「東洋のエルサレム」と呼ばれたように、キリスト教が深く根を下ろしている所です。日本の占領期には、神社参拝は言うに及ばず、皇居のある東方に向かって敬礼させる東方遥拝など、ありとあらゆる弾圧が縦横に加えられました。私は平壌の西門に近い景昌里の羅最燮氏の家で伝道生活を始めました。その人は南にいた時から知っていた教会の執事です。
最初の日、近くの子供たちを集めて世話をすることから始めました。子供たちが来れば、『聖書』のみ言を付け加えた童話を聞かせて、一緒に遊びました。子供であっても必ず敬語を使い、真心を込めて世話しました。そうしながら、私が伝えたい新しいみ言を誰かが聞きに来るだろうと待ったのです。ある時は一日中門の外を眺めて、人を懐かしく思ったりもしました。そうやってじっと待っていると、やがて篤実な信仰心を持った人たちが私を訪ねてくるようになりました。その人たちを迎えて、私は夜通し新しいみ言を教えました。訪ねてくる人には、三歳の子供であろうと腰の曲がった目の遠い老人であろうと、愛の心で敬拝し、天に対するように仕えました。年取ったお爺さん、お婆さんが訪ねてきても、夜遅くまで話をしました。「なんだ、年を取った老人なので嫌だな」というような思いを持ったことは一度もありません。人は誰でも尊いのです。人が尊いことにおいて、老若男女に差別はありません。
二十六歳の若々しい青年がローマ人への手紙やヨハネの黙示録を教えるのですが、その話が今まで聞いたことのない内容なのか、志のある者が一人、二人と集まり始めました。毎日のように来ては、喋ることもなく、ただ話だけを聞いていった器量の良い青年である金元弼は、そうやって私の一番目の弟子になりました。私は、平壌師範学校を卒業し教鞭を執っていた彼と二人で、交代でご飯を炊いて食べ、師弟の絆を深めました。
私は一度『聖書』の講義を始めると、信徒たちがやることがあると言って先に席を立たない限りは休みませんでした。精いっぱいの情熱を注いで教えたので、体中から汗が滝のように流れました。みんなに分からないように、外に出て服を脱いで絞ると、服から水がぽたぽたと落ちます。暑い夏だけではありません。雪の降る厳寒の季節でもそうでした。そうやって全身全霊を込めて教えました。
礼拝を捧げる時は必ずきれいな白い服を着ました。讃美歌を数十回繰り返して歌い、情熱的な礼拝を捧げました。参会者が感動にあふれて涙を流すので、世間は私たちの教会を指して「泣く教会」とも呼んだのです。礼拝が終わると、一人一人が受けた恵みを証しします。証しをしている間、参会者は皆、恵みによって体が天に舞い上がるような体験をしました。
私たちの教会には、入神する人、予言する人、異言を語る人、また異言を通訳する人等々、霊通する人が多く現れました。時として私たちの教会に合わない人が来ていたりすると、霊通した人が目を閉じたままその人のところに行って、肩をバーンと叩きます。すると、叩かれた人は急に涙や鼻水を流して、悔い改めのお祈りをするようになります。そうやって熱い聖霊の火がサーッと通り過ぎていくのでした。
聖霊の火の役事(神のみ業、神霊の働き)が起こると、長い間患っていた病気がきれいに治ったりもしました。特に、私が残したご飯を食べて胃腸病が治ったという人の話が周囲に広まると『教会のご飯は薬ご飯』と言って、私が残したご飯を待つ人も大勢現れました。
このような聖霊の体験が知られてから、教会の門を閉めることができないほど信者の数が増えました。池承道ハルモニ (お婆さん) や玉世賢ハルモニは、夢の中で「若い先生が南から上がってきて、万寿台を渡ったところにいる。行って会いなさい」という言葉を受けて、訪ねてきました。誰かが伝道したとか導いたとかではなくて、天が教えた住所を聞いて、路地を歩き回って探し当て、「夢でお会いした方がまさに先生です」と言って喜んだのです。神学を勉強した牧師たちも私を訪ねてきました。私は彼らの顔だけ見ても、何が気がかりで訪ねてきたかが分かりました。何も聞かずに彼らの疑問に答えを示してあげると、喜びながら、びっくりして感激に震えるばかりでした。
自ら悟って体験した話から神のみ言を説いたせいか、今まで理解できずに疑問だった部分がすっきりと解決されたと言って、多くの人たちが喜びました。大きな教会に通った人の中には、私の説教を聞いて、通っていた教会をやめて私たちの教会に来る人もいました。平壌で一番有名な章台峴教会の中核メンバー十五人が一度に私を訪ねてきて、教会の長老たちが激しく抗議してきたこともあります。
金仁珠夫人の義父は平壌で有名な長老でした。しかし彼女は義父の教会には行かず、家が義父の通っていた教会のそばだったので、夫の家族に気づかれないように、庭の甕置き台を上がって、家の塀を越えて私たちの教会に来たのです。夫人はおなかに娘がいる体で、二尋 (約三・六四メートル)ほどの高さになる塀を、危険を顧みずに跳び越えて来ました。これが元で、彼女は長老である義父母から激しい迫害を受けました。私もそのことを知っていました。ひどく胸が痛む日は、信者を夫人の家に送って様子を」かがわせましたが、そのような日は間違いなく義父から鞭打たれていました。よほどひどく曜かれたのか夫人は血涙を流していました。
ところで、夫人は食口 (家族の意。教会の信徒を、親しみを込めてこう呼ぶ) たちが門の外に立っていると少しも痛くいと言います。「先生は、私が鞭打たれるとどうしてお分かりになったのですか。食口がいると私は痛みもなく、叩く義父の方がくたびれてどうすることもできないのです。一体どうしたことでしょうか」と話していました。
鞭を振るい、柱に縛り付けておいても、嫁が懲りずに私たちの教会に行くようになると、金仁珠夫人の家族が教会にやって来て、いきなり私を殴ったりもしました。服が破れ、顔が大きく腫れ上がりましたが、私は一度も刃向かいませんでした。刃向かえば、夫人がもっと困難になるとよく知っていたからです。
大きな教会に通う信徒たちがどんどん抜け出してくると、既成キリスト教会の牧師たちは、私をねたんで警察に告発するようになりました。ただでさえ宗教を目の上のこぶと見て一掃しようと狙っていた共産党当局は、格好の口実を得て私を捕らえにかかりました。
一九四六年八月十一日、私は「南から上がってきたスパイ」の汚名を着せられて、平壌の大同保安署に連行されました。南の李承晩が半島北部の政権に欲を出して密かに北に派遣したスパイだと決めつけたのです。
監獄暮らしといっても特に恐ろしくはありませんでした。経験があったからでしょうか。その上また、私は監房長と親しくなるのが上手です。二言三言話をすれば、どんな監房長でもすぐに友達になってしまいます。誰とでも友達になれるし、愛する心があれば誰でも心を開くようになっています。
数日経つと、一番端っこに座っている私を、監房長が上の場所に引っ張ってくれました。便器のそばのとても狭い隅っここそ私が一番好む場所なのに、しきりにもっと良い場所に座れと言ってきます。いくら嫌だと言ってもどうしようもないことでした。
監房長と親しくなったら、今度は監房の住人を一人一人調べてみます。人の顔はその人の何もかもを物語ってくれます。「ああ、あなたはこうだからこのような人であり、あなたはああだからあのような人である」と言って話を始めれば、誰もが驚きました。初めて会った私が心の中を言い当てるので、内心は嫌っても認めざるを得ません。
誰であっても心を開いて愛情をもって接するので、監房でも友人ができ、殺人犯とも親しくなりました。やるせない監獄暮らしだったとはいえ、私には私なりに意味のある鍛錬期間でした。この世の中に意味のない試練はありません。
監獄ではシラミもノミも皆友達です。獄中の寒さは格別なものがあって、囚人服の仮縫いのところから糸を伝わって行き来するシラミを捕まえて一箇所に並べると、シラミどうしが互いにへばり付き合って丸くなるほどです。それをフンコロガシのようにごろごろ転がせば、互いに離れまいと必死になります。シラミはもともと入り込む性質があって、互いに頭を突き合わせてくっついてはお尻だけ出しているので、この光景を見るのも面白くてたまりません。
世の中にシラミやノミを好きな人はいないでしょう。しかし、監獄ではシラミやノミも貴重な話し相手になります。南京虫やノミを見る瞬間、ふと悟る啓示がありますが、それを逃してはなりません。神がいつ何を通して語られるか予測できません。南京虫やノミであっても貴く思って調べてみることができなければなりません。
監獄にいる問、罪を自白せよと数限りなく殴られました。しかし、血を吐いて倒れ、息が絶えそうになる瞬間にも、気を失わずに耐え忍びました。腰が折れたかと思うほどの激しい苦痛が襲うと、「天のお父様、私をちょっと助けてください」という祈りが自然と出てきます。そうすると再び気を取り直して、「お父様、心配なさらないでください。文鮮明はまだ死にません。こんなふうにみすぼらしく死んだりしません」と言って、堂々と振る舞いました。そうです。私はまだ死ぬ時ではありませんでした。私の前には完遂しなければならないことが山のようにあったし、私にはそれらをやり遂げる使命がありました。拷問ごときに屈服して同情を買う程度のいくじなしの私ではありません。今も私の体にはその時できた傷跡がいくつか残っています。肉が削げ、血が流れた箇所は、今はもう新しい肉が付きましたが、その日味わった激しい苦痛は、傷跡の中にそっくりそのまま残っています。私は、その日の苦痛が染み付いた傷跡を眺めて誓ったこともあるのです。
「この傷を持ったおまえは必ず勝利しなければならない」
ソ連の調査官まで出てきて私を糾弾しましたが、罪がないのでどうしようもありません。結局、およそ三カ月後の一九四六年十一月二十一日、捨てられるようにして釈放されました。拷問であまりに多くの血を流して命の危険がある状態でしたが、信徒たちがよく世話してくれました。無条件に尽くして私に生命を与えてくれました。
こうして、私はもう一度気力を振り絞って教会の仕事を始めました。教勢が急に大きくなったのは、それから一年を過ぎた頃です。ところが、既成キリスト教会はそのような私たちを放っておきませんでした。既成教会の信徒たちがより一層私たちの教会に集まるようになると、反対する既成キリスト教会の牧師八十人以上が、共産党当局に投書して私を告発しました。これを受けて、私は再度共産党によって連行されたのです。平壌内務署に捕縛された日が一九四入年二月二十二日でした。鎖を付けて引かれていき、四日目に頭を刈られました。その時に私の頭を刈った人の姿まで生き生きと覚えています。教会を切り盛りしていた間に長く伸びた髪の毛が、ぼとりと床に落ちました。
捕縛されるやいなや、またしても鋭い拷問が開始されました。拷問を受けて倒れるたびに、「私が受ける鞭は民族のために受けるのだ。私が流す涙は民族の痛みを代表して流すのだ」という思いで耐え忍びました。極度の苦痛で気を失いそうになると、間違いなく神様の声が聞こえました。神様は息が絶えるか絶えないかという瞬間に現れます。
公判は四月七日でした。本来、拘禁されて満四十日になる四月三日が公判の予定でしたが、七日に延期されたのです。公判廷には、北で有名な牧師たちがぞろぞろと集まってきて、私にありとあらゆる悪口を浴びせました。宗教はアヘンだと言う共産党も私を嘲笑しました。公判を見に来た教会の信徒たちは、弁護側の席で物悲しく泣いていました。まるで子供や夫が世を去ってしまったかのように哀切な祈りを捧げていました。しかし、私は涙を流しませんでした。私を見て身悶えして泣いてくれる信徒たちがいるので、天の道を行く者として少しも寂しくなかったのです。「私は不幸な人ではない。だから泣いてはならない」と思いました。判決を受けて公判廷を後にする際、彼らに手錠のかかった手を振ってあげると、手錠からチャランチャランと音がしました。その音がちょうど鐘の音のようでした。私はその日すぐに平壌刑務所に収監されました。