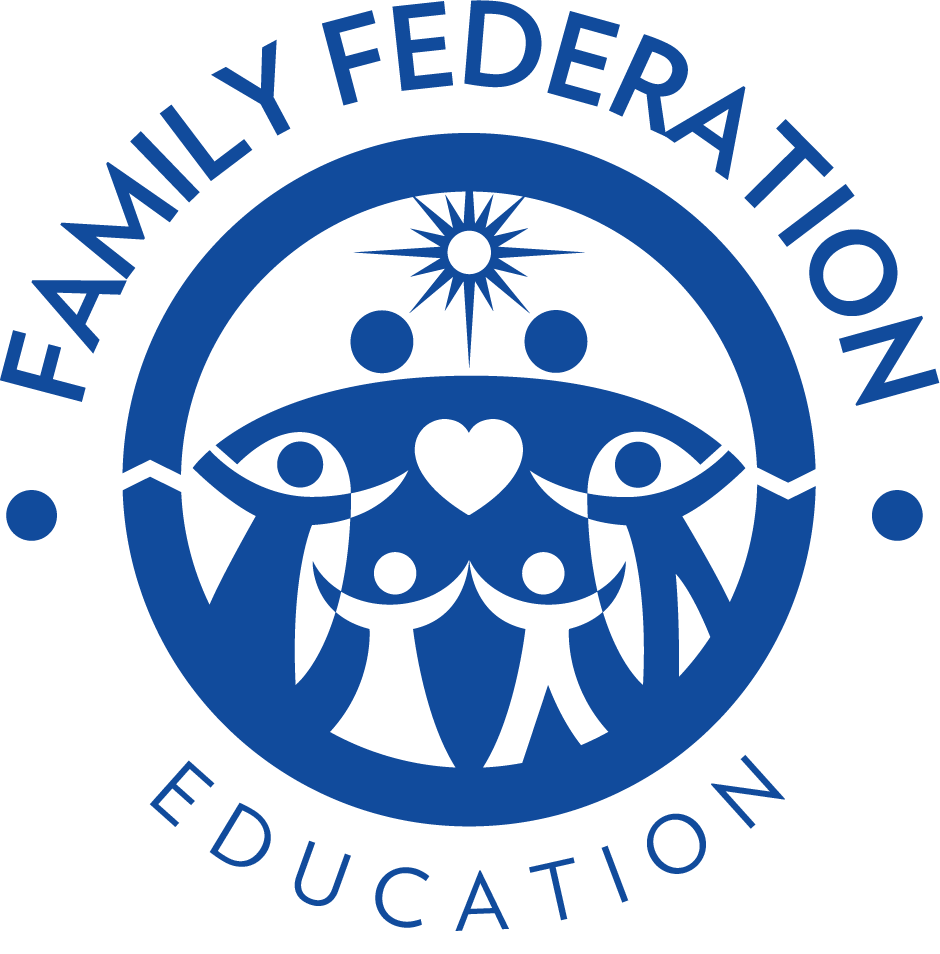平和を愛する世界人として 第20話
雪の降る興南監獄で
監獄で、食べ物の次に恋しかったのが針と糸でした。労働でぼろぼろになった衣服を繕おうとしても、針と糸がないとそれができません。そうなると、獄中生活が長くなればなるほど乞食のような格好になってしまいます。特に、興南の冷たい冬の風を何とかしようとしたら、穴の空いた衣服をそのままにはしておけず、そんな時は道で拾った小さな布切れでもとても貴重です。鉄屑が付いた布であっても、みんなが争って拾おうとして大騒ぎになります。布は何とか確保できても、針を手に入れるのはさらに大変でした。ところが運のいいことに、硫安のかますを運ぶ途中に、偶然針一本がくっついてきたのを見つけました。田舎から持ってくるかますに、なぜか混ざっていたのです。その時から、私は興南監獄の針仕事屋になりました。針を手に入れたのがうれしくてたまらず、毎日のように他の人のズボンや股引を縫ってあげました。
肥料工場は、真冬でも汗がたらたら流れるほど暑く、冬でもそうなので、真夏の暑さは想像を絶すると言ってよいでしょう。それでも私は、一度もズボンの裾を巻き上げて向こう脛を出したことがありません。一年で一番蒸し暑い時期でも、必ず裾の紐を結んで働きました。他の人がズボンを全部脱いで放り投げ、下着姿で働くときでも、私はちゃんとしたズボン姿で働きました。
一日工場で仕事をしてくると、体中が汗と肥料の粉でべとべとになります。大部分の人が仕事を終えるやすぐに服を脱いで、工場から流れてくる汚い水で体を洗いました。しかし、私は一度も体を出して洗うことをしませんでした。その代わり、配給でもらうコップ一杯の水を夜の間残しておいて、まだみんなが眠っている明け方に起きて、タオルに水を濡らして体をふきました。明け方の霊気を集めてお祈りをするためでもありますが、自分の尊い体をむやみに人前にさらしてはならないという考えから、そのようにしました。
監獄では三十六人が一部屋の監房に生活しましたが、非常に狭い部屋の隅に置かれた便器の横が私の居場所でした。夏になれば水があふれて湿っぽくなり、冬になれば氷が凍って、誰もが嫌がる場所です。便器といっても蓋のない小さな入れ物があるばかりで、その臭気は筆舌に尽くしがたいものがありました。
塩のスープに蕎麦の握り飯を食べた囚人は、ともすれば下痢を起こしました。
「ああっ、おなかが!」
おなかをかばって便器まで刻み足で走ってきた囚人が、お尻を出すやいなや、慌てふためいて液便をザーッと出すので、便器の横にいる私はややもすると液便を被りました。
全員が寝静まった夜中にもおなかが痛む人はいるようです。
「あっ、痛っ」
と言って、足を踏まれた人の悲鳴が聞こえると、私は素早く起きて隅に行って座ります。人を踏んづけて急いで便器まで駆けてきた人は、そこに来てお尻を出す前に下痢便を漏らし、無理にでもそのまま我慢して排泄するので、飛沫が飛び散って悲惨なことになります。寝入っていて、きれいによけられない日は、そのまま被るしかありません。それでも、四六時中液便が跳ねるその隅の場所を、私の居場所と思い定めて生活しました。「よりによっていつもそんな所に座るのはどうしてか」と他の囚人に聞かれると、「ここが一番楽です」と答えました。わざとそうしたということではないのです。その場所に座ると本当に気持ちが楽になりました。
私は文学や芸術を特別なものだとは考えません。何であっても私と心が通じて親しくなれるなら、文学であり芸術なのです。便所で便が落ちる音が美しく楽しく聞こえれば、それもまた音楽と異なるところはありません。同様に、便器の前で横になっている私に跳ねた液便も、私の考えに従えば素晴らしい芸術作品になることがあります。
当時、私の囚人番号が五九六番でした。そこで人々は私を「オグリュク」と呼びました。夜、眠ることができず、横になって天井を眺めて、「オグリュク、オグリュク……」と独り言を言いながらするすると舌を転がして発音すれば、「オグリュク」が「オグル(韓国語で「憤慨」の意味)」に聞こえました。私は本当に「悔しい」囚人でした。
共産党は、監獄の中に「読報会」なるものを作って自己批判させ、保安隊によって囚人の一挙手一投足を監視しました。そして、毎日、その日に学んだことを感想文として書けと言ってきました。しかし、私はただの一文も書きませんでした。「父なる金日成首領が私たちを愛してくださり、毎日のようにご飯と肉のスープを与え、このようにいい暮らしができるようにしてくださって感謝です」などという感想文は、絶対に書くことができませんでした。いくら死が目の前にちらついたとしても、無神論者である共産党幹部に感想文を捧げることなど、できない相談でした。私は感想文を書く代わりに、監獄で生き残るため、人よりも数倍熱心に働きました。一等労働者になることだけが、感想文を書かなくとも監獄生活を耐え抜くことのできる道だったからです。おかげで一等模範囚になって、共産党幹部が出す賞まで受けました。
監獄にいる問、何度か母が訪ねてきました。定州から直接興南に行く汽車はないので、乗り換えながら二十時間もかけて来るのです。その苦労は並大抵のものではありません。若い盛りに獄舎につながれた息子に食べさせるために、親族の八親等まで頼って米を一握りずつ集めて、炒り粉 (はったい粉) にして持ってきてくれました。面会所の鉄条網の外で息子の顔に出くわした母は、涙を流していました。はるばる遠く興南までやって来た強靭な母親が、監獄の息子を見るなり胸が詰まり、顔も上げることができずに泣き続けました。私の姿があまりにみすぼらしかったのか、いくら強靭な女性であっても、苦痛のただ中にいる息子の前では弱い母親にすぎませんでした。
母は、私が結婚する時に着た紬のズボンを持ってきてくれました。囚人服は硫安で溶けてぼろぼろになって肌が見えていましたが、私は母がくれた紬のズボンを穿かずに他の囚人にあげてしまいました。親族を頼って準備してきたはったい粉も、母が見ている前で囚人たちにすべて分け与えました。息子に食べさせ、着させようと真心を込めて作ってきた食べ物と衣服を、全部赤の他人に与えてしまうのを見て、母は胸をかきむしって泣きました。
「お母さん、私は文なにがしの息子ではありません。文なにがしの息子である前に、大韓民国の息子です。また、大韓民国の息子である前に世界の息子であり、天地の息子です。ですから、彼らを先に愛してから、お母さんの言葉を聞き、お母さんを愛するのが道理です。私は度量の狭い男ではないので、そういう息子の母親らしくしてください」
氷のように冷たい言葉を浴びせたのですが、母の目を見る私の胸は張り裂けんばかりに痛かったのです。寝ても母が懐かしくて目覚めるほどだったので、弱くなりそうな心を落ち着かせなければなりませんでした。神の仕事をする者には、私的な母子の因縁よりは、たったの一人であっても暖かく着せ、もっとおなかいっぱい食べさせることのほうが重要だったからです。
私は監獄にいても、人々と時間を見つけては会話を楽しみました。私の周りはいつも話を聞きに集まった人たちでいっぱいでした。おなかが空き、寒さに震える獄中生活であっても、通じる人たちとの交流は温かいものでした。興南で結んだ縁で、私は十二人の同志であると同時に生涯を共にする人を得ました。その中には以北五道連合会の会長だった有名な牧師もいました。彼らは、命の危険と隣り合わせの環境にあって、血肉よりもっと濃い絆で結ばれた私の骨と肉のような存在でした。彼らがいたので獄中生活は空しくありませんでした。明け方になると、私は彼らの名前を一人一人呼んで真心を捧げ、平壌にいる教会信徒のためにも毎日三回以上名前を挙げてお祈りしました。彼らがズボンの胴回りに隠して私に取っておいてくれたはったい粉一握りを、数千倍にして返してあげなければならないと思いました。