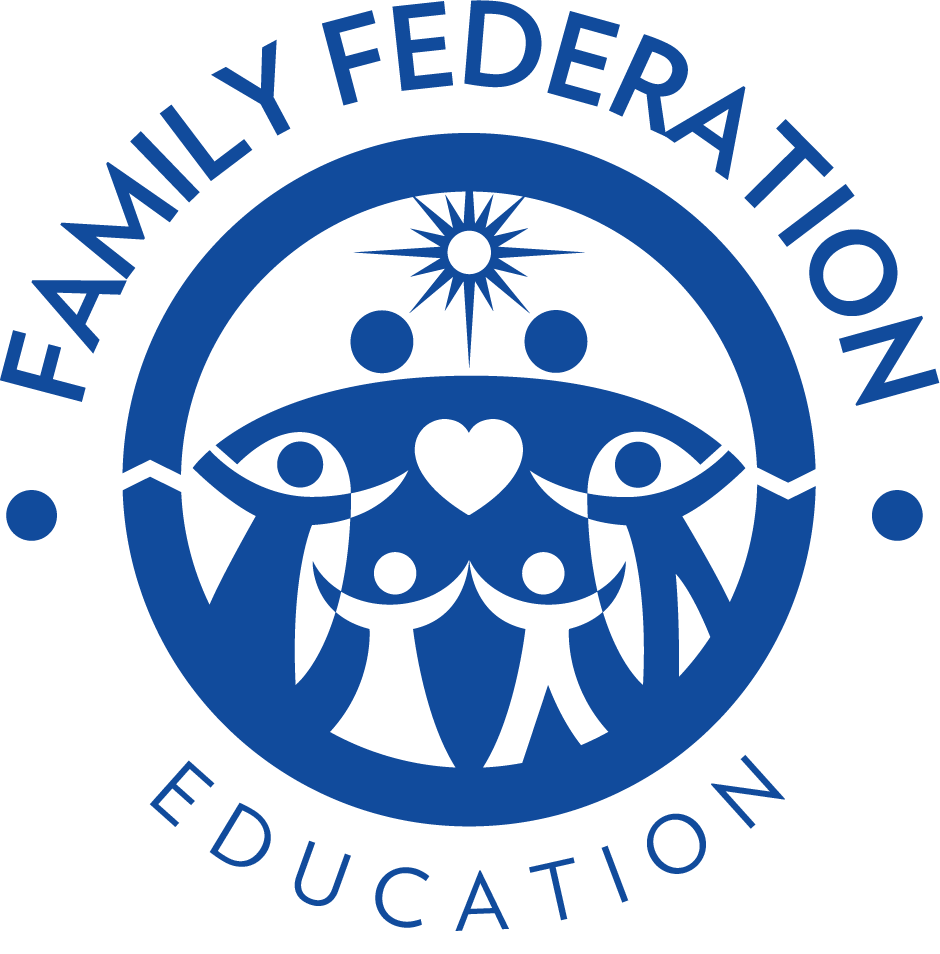平和を愛する世界人として 第13話
巨大な秘密の門を開ける鍵
故郷で山という山は全部足を運んで登ったように、ソウルも隅々まで行かなかった所がありません。その頃、ソウル市内を電車が走っていました。電車賃は五銭でしたが、それさえもったいなくて、いつも歩いて行きました。蒸し暑い夏の日は汗をたらたら流して歩き、極寒の冷たい冬は肉を抉るような風をくぐり抜けるようにして歩きました。もともと足が速い私は、黒石洞から漢江を渡って鍾路の和信百貨店まで四十五分あれば着きました。普通の人には一時間半ほどの道のりですから、どれだけ早足だったか想像がつくでしょう。浮いた電車賃は貯めておいて、私以上にお金に困った人に分け与えました。出すのが恥ずかしいくらいの微々たる金額だとしても、大金を出せなくて申し訳ないという気持ちで、そのお金が福の種になるようにと思って渡しました。
四月には故郷からきちんと学費を送ってきましたが、生活が苦しい周囲の人たちを見過ごしにできず、五月になる前に全部なくなりました。学校に行く途中、息も絶え絶えの人に出くわしたことがあります。かわいそうに思うと足が止まってしまい、その人を背負ってニキロほど離れた病院に向かって走り出しました。運良く財布に入っていた学費の残りで治療費を払うと、あとはもうすっからかんです。今度は自分の学費が払えなくなり、学校から督促を受けることになりました。それを見て、友人がお金を一銭、二銭と集めてくれました。その時の友人は生涯忘れられません。
助け合うこともまた、天が結んでくれる因縁です。その時はよく分からなくても、後で振り返ってみて、「ああ、それで私をその場に送られたのか」と悟るようになりました。ですから、突然私の前に助けを乞う人が現れたら、「天がこの人を助けるようにと私に送られたのだ」と考えて、心を込めて仕えます。天が「十を助けなさい」と言うのに、五しか助けないのでは駄目です。「十を与えよ」と言われたら、百を与えるのが正しいのです。人を助けるときは惜しみなく、財布をはたいてでも助けるという姿勢が大切です。
ソウルに来て、ケピトック(風餅)というお菓子を初めて見ました。色や模様が美しいので、「ああ、こんなに美しい餅がたくさんあるなあ」と言って、口に入れて噛むと、中の空気が抜けて、ぺちゃんこに潰れるではありませんか。その時思いました。ああ、ソウルという所はそのままこのケピトソクのようだ、と。「抜け目のないソウルっ子」という言葉がなぜ生まれたのか、分かった気がしました。ソウルは外から眺めると、地位の高い立派な職業の人ばかりいる富者の世の中に見えますが、その実態は貧者の天下です。漢江の橋の下にはぼろぼろの服を着た乞食があふれていました。私は漢江の橋の下の貧民窟を訪ねて行き、彼らの頭を刈って心を通わせました。貧しい人は涙もろいのです。胸の中に溜まりに溜まった思いが高ずるのか、私が一言声をかけても泣き出して、大声で泣き叫びました。手には、ぽりぽり掻くと白い跡ができるほど、べっとりと垢がこびり付いています。物乞いでもらってきたご飯をその手でじかに私にくれたりもしました。そんな時は、汚いとは言わずに喜んで一緒に食べました。
ソウルにいた時も熱心に教会に通いました。最初は黒石洞五旬節教会に通い、漢江の向こう側 (北側)にあった西氷庫五旬節教会にも通いました。その後、内資洞 (現在のソウル特別市鍾路区内)のイエス教会と黒石洞にあった明水台イエス教会に通いました。西氷庫洞(現在のソウル特別市龍山区内) に行こうとして漢江の橋を渡ると、寒い冬の日は「パーン!ジジジジー!」と氷が割れる音がしたものです。
教会で日曜学校の先生を務めたことを思い出します。私の話は抜群に面白くて、子供たちがとても喜びました。今は年を取って冗談を言う才能もなくなりましたが、その当時は面白おかしい話もよくして、子供たちは打てば響くように反応してくれました。私がアーンアーンと泣けば子供たちもアーンアーンと泣き、私がハッハッハと笑えば子供たちもハッハッハと笑います。私の後ろをぞろぞろ付いて回るほど人気がありました。
明水台の裏側に瑞達山があります。瑞達山の岩に登って、しばしば夜を徹して祈りました。寒くても暑くても、一日も休まず祈りに熱中しました。一度祈りに入れば涙と鼻水が入り混じるくらい泣き、神様から受けたみ言を胸に抱いて、何時間も祈りだけに集中しました。神様のみ言はまるで暗号のようで、それを解こうとすればより一層祈りに没頭しなければなりません。今考えると、その時すでに、神様は秘密の門を開ける鍵を親切に与えてくださったのに、私の祈りの不足ゆえにその門を開けることができませんでした。そういう訳で、ご飯を食べても食べた気がせず、目を閉じても眠れませんでした。
一緒に下宿していた友人たちは、私が山に登って夜通し祈っていることはよく知らないようでした。それでも、他の人とは違う何かが感じられたのか、私に一目置いていました。しかし私は、平素はおどけた言動をして仲良く過ごしたものです。私は誰とでも気持ちがすっと通じます。お婆さんが来ればお婆さんと友達になり、子供たちが来れば子供たちとふざけたりして遊びます。相手が誰であっても、愛する心で接すればすべて通じるのです。
黒石洞の頃、早朝祈禧会で私の代表祈疇に感化され、私を訪ねてきて親しくなった李奇完おばさんとは、この世を去る時まで四十数年間、友情を分かち、友として交流しました。妹の李奇鳳おばさんは、私が下宿した家の女主人でした。下宿の掃除で何かと忙しそうにしていましたが、いつも私に温かく接してくれました。私によくすれば自分の心が楽になると言って、おかずの一つでももっと食べさせようと気を配ってくれました。無口で、別段面白みもない私を、なぜそんなふうにかわいがってよくしてくれたのか分かりません。後日、私が京畿道警察部に収監された時は差し入れもしてくれました。今も李奇鳳おばさんを思えば胸が温かくなります。
自炊の家の近所で小さな店を出していた宋おばさんも、その頃の大事な恩人です。おばさんは、故郷を離れて暮らすのはおなかが空いて大変だろうと言って、店の売れ残りがあると何でも持ってきてくれました。小さな店を切り盛りしてやっと食べている立場なのに、私にはいつも厚い情けをかけてくれて、食べ物を用意してくれました。
漢江の川辺で礼拝を捧げた日のことです。昼食時間になって、会衆はばらばらに座ってご飯を食べ始めました。昼食を取らない私は、その中にぼんやり座っていても仕方ないので、一人だけすっと後ろに離れて、川辺の石の小山に座っていました。それを見た宋おばさんが、パン二個とアイスケーキを二個持ってきてくれました。それがどれだけありがたかったかしれません。一つ一銭で、全部で四銭にしかならないものでしたが、おばさんの心遣いは今も私の心に刻まれています。
いくら小さなことでも、いったんお世話になったら生涯忘れることができません。年が九十歳になった今も、いつ誰が何をしてくれたか、また、いつ誰がどのようにしてくれたか、すらすら話すことができます。私のために労苦を惜しまず、陰徳を施してくれた人たちを生涯忘れることはできません。
陰徳を受けたときは、必ず、もっと大きくして返すのが人の道です。しかし、その人に直接会えないこともあるでしょう。恩恵を施してくれた人に直接会えなかったとしても、大事なのはその人を思う心です。ですから、その人に会えなくても、受けた恵みを今度は他の人に施そうという一途な心で生きるのがよいのです。