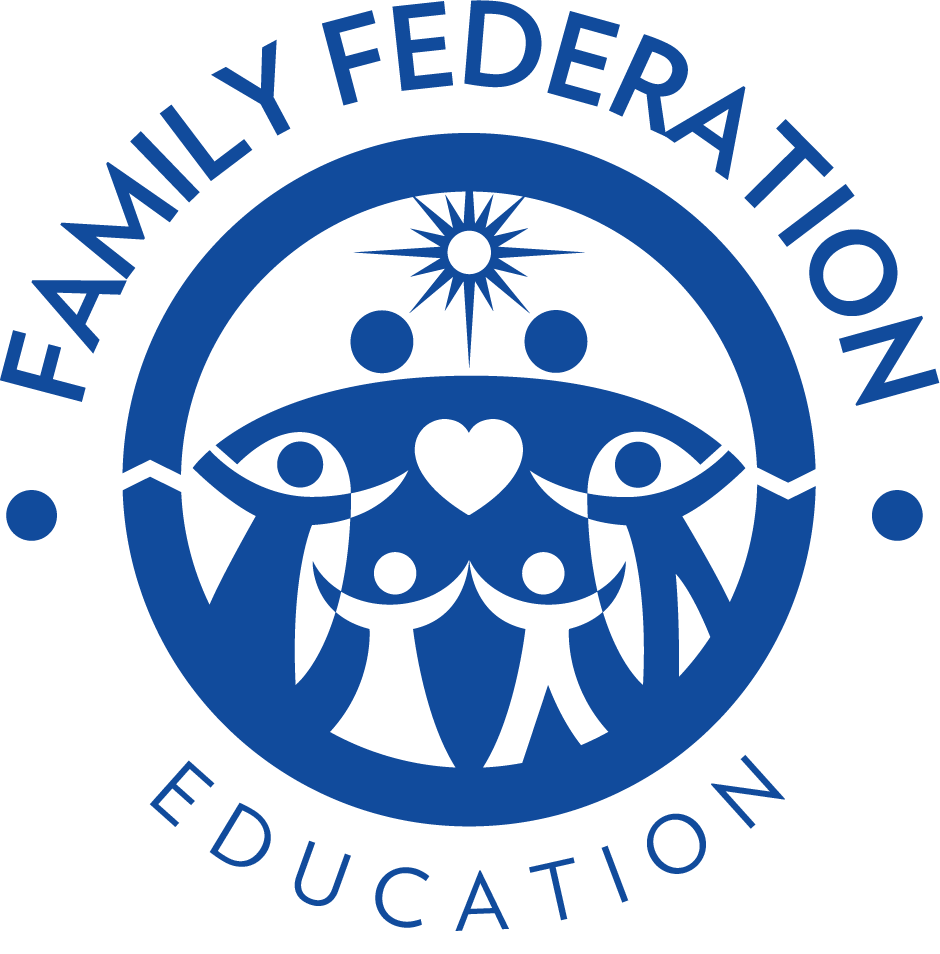平和を愛する世界人として 第3話
人に食事を振る舞う喜び
私の目はとても小さいのです。どれほど小さいかというと、母は私を産んで、「うちの赤ちゃんには目があるのか、ないのか」と言って、わざわざ目を広げて見ようとしたそうです。すると、生まれたばかりの私が目をぱちぱちしたので、「あれまあ、目があるにはあるんだ!」と言って喜んだといいます。そのように私の目が小さかったために、幼い頃は「五山の家の小さな目」と呼ばれました。
それでも、目が小さくて貧相だという話は聞いたことがありません。むしろ少しでも観相の分かる人は、私の小さな目に宗教指導者の気質が現れていると言います。カメラの絞りも穴を狭めるほどより遠くを見ることができるように、宗教指導者は人より先を見通す力がなければならないので、そのように言うのでしょう。私の鼻も変わっているのは同様で、一見して誰の言葉も聞かない頑固一徹の鼻です。観相は決していい加減なものではなく、私が生きてきた日々を振り返ってみると、「このように生きようとして、そのような顔に生まれた」と言うことができます。
私は平安北道定州郡徳彦面上思里二二二一番地で、父は南平文氏の文慶裕、母は延安金氏の金慶継の次男として生まれました。三・一独立運動が起こった翌年の一九二〇年陰暦一月六日が、私が生まれた日です。
上思里には曾祖父の代に引っ越してきたそうです。数千石の農業に直接従事して、独力で暮らしを立てて家門を起こした曾祖父は、酒もたばこも口にせず、そのお金でよその人にご飯一杯でも多く食、べさせようとし、そうすることに生き甲斐を感じる人でした。「八道江山(全国)の人に食事を振る舞えば、八道江山から祝福が集まる」1これが亡くなる際に遺した言葉です。そんなわけで、わが家の奥の間はいつもたくさんの人でごった返していました。「どこそこの村の文氏の家に行けば、ただでご飯を食べさせてくれる」と村の外にまで知れ渡っていたのです。母はやって来る人たちのつらい世話をてきぱきとしながら、不平を一度も言いませんでした。
休む間もなく熱心に働いた曾祖父は、暇ができると草鮭を編んで市場に出して売ったり、年を取ってからは「後代にわが子孫が良くなるようにしてください」と祈りながら、アヒルを数匹買っては放してやったりしました。また、奥の間に漢文の先生を招いて、近所の若者たちに文字を無料で教えるようにしました。そこで村人たちは、曾祖父に「善玉」という号を付けて、わが家を「福を受ける家」と呼びました。
しかしながら、曾祖父が亡くなって私が成長する頃には、豊かだった財産はすべてなくなり、ただ幾匙かのわずかなご飯を食べて暮らす程度になりました。それでも、人に食事を振る舞う家風だけは相変わらずで、家族が食べる分がなくても人を先に食べさせました。おかげで、私がよちよち歩きを始めて最初に学んだことが、まさしく人にご飯を食べさせるということでした。
日本占領期の頃、満州に避難する人々が通った町が平安北道の宣川です。わが家はちょうど宣川に行く一級道路(幹線道路)の近くにありました。家も土地も日本人に奪われて、生きる手立てを求めて満州に向かった避難民が、わが家の前を通り過ぎていきました。母は八道(李氏朝鮮時代、全国を威鏡道、平安道、江原道、黄海道、京畿道、忠清道、慶尚道、全羅道の八道に区分したことに由来する言葉)の各地からやって来て家の前を通る人のために、いつでもご飯を作って食べさせました。乞食がご飯を恵んでくれと言ってきて、すぐにご飯を出さなければ、祖父がまず自分のお膳をさっと持って行きました..そのような家庭に生まれたせいか、私も生涯ご飯を食べさせる仕事に力を注いできました。私には、おなかを空かした人たちにご飯を食べさせる仕事が他のどんなことよりも貴く重要です。ご飯を食べる時、ご飯を食べられない人がそこにいれば、胸が痛く、喉が詰まって、スプーンを持つ手がそのまま止まってしまいます。
十歳の時でした。大みそかの日になって、村じゅう餅を作るのに大忙しだったのに、暮らし向きが困難で食べる物にも事欠く村民がいました。私はその人たちの顔が目に焼き付いて離れず、一日中、家の中をぐるぐる回ってどうしようかと悩んだあげく、米一斗(一斗は十升、約十八リットル)を担いで家を飛び出しました。家族に気づかれないように米袋を持ち出そうとして、袋に縄を「本結んでおく余裕もありませんでした。それでも、米袋を肩に担いだまま、つらさも忘れて、勾配が険しい崖道を二十里(約八キロメートル。十朝鮮里は日本の一里、約四キロメートルに相当する)も跳ねるように駆けていきました。おなかを空かした人たちを腹いっぱい食べさせることができると思うと、気分が良くて、胸がわくわくしました。
わが家の横には石臼を使った精米所がありました。中の小米が外に漏れないように精米所の四方をしっかり囲むと、冬にも吹き抜ける風がなくて、とても暖かでした。家のかまどから炭火を分けてきて火を起こすと、オンドルの部屋よりも暖かくなります。そんなわが家の横の石臼の精米所に居場所を定めて、冬の季節を過ごす者たちが何人かいました。八道を転々として物乞いして歩く乞食たちです。彼らが聞かせてくれる世の中の話が面白くて、ちょくちょく石臼の精米所に足を運んだものです。母は息子の友達となった乞食の食事まで一緒に作って、精米所にお膳を持ってきてくれました。分け隔てなく同じ皿をつつき、同じご飯を食べ、毛布一枚に一緒にくるまって、共に冬を過ごしました。真冬が去って春になり、彼らが遠くへ行ってしまうと、また戻ってくる次の冬が待ち遠しくてなりませんでした。
体がぼろをまとっているからといって、心までぼろをまとっているわけではありません。彼らには、明らかに温かい愛がありました。私は彼らにご飯をあげ、彼らは私に愛を施してくれました。彼らが教えてくれた深い友情と温かい愛は、今に至るも私の大きな力になっています。
世界を回って、貧しさとひもじさで苦痛を味わう子供たちを見るたびに、人々にご飯を食べさせて少しも惜しむことがなかった祖父の姿が脳裏に浮かびます。