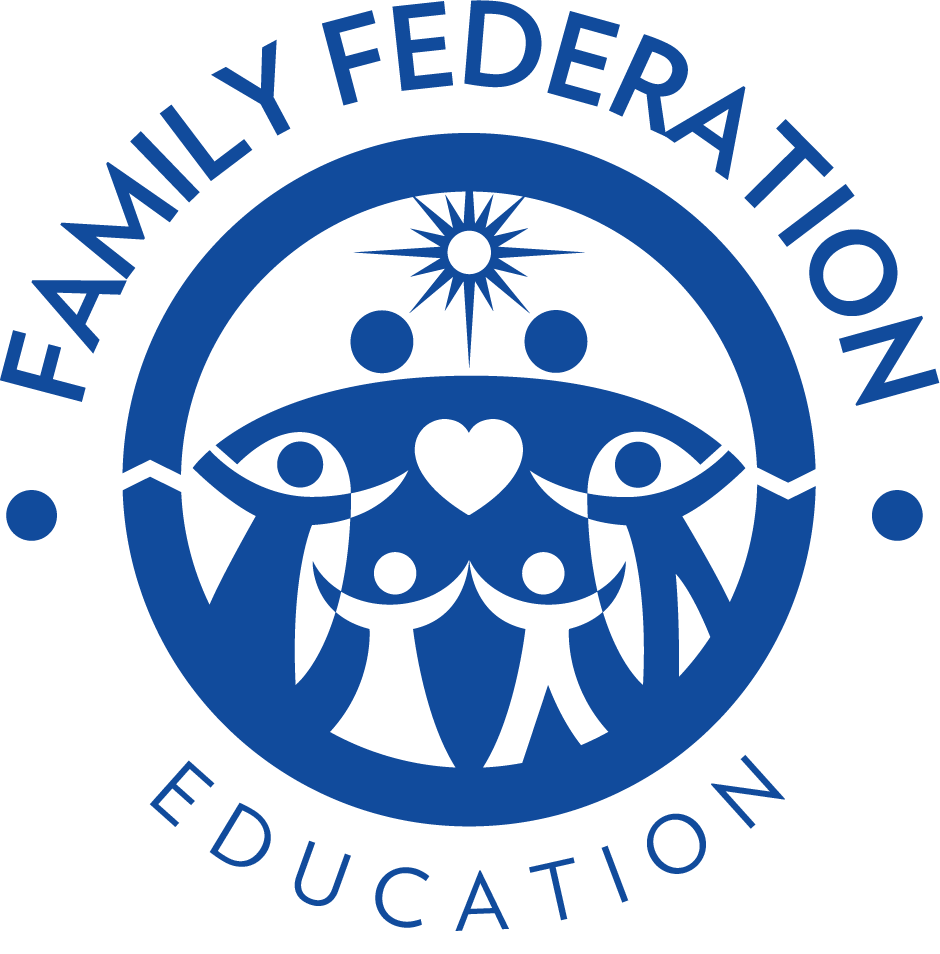真の父母経 第180話
22 興南の肥料工場でする仕事は重労働です。一般社会の人でも、一週間に一度ぐらいは豚肉を食べなければなりません。豚肉は脂が溶けていきます。牛肉は脂が固まりますが、豚肉の脂は流れ落ちるので、細胞を洗浄する作用があるのです。肥料の成分が体の中に入って固まってはいけません。ですから、人々は、一週間に一度くらい豚肉の脂身を無性に食べるのです。しかし、そこに肉があるでしょうか。「御飯でもたらふく食べられたらよい」と思うのです。
朝御飯は、お父様なら三さじも食べれば終わりです。口を大きく開けて食べれば、三さじにしかならないというのです。それを食べて八時間、重労働をするのです。
収容者たちは、朝御飯を食べて工場に出掛けるのですが、工場まで一里以上の道のりです。一里を超える距離を歩いていけば、足もふらつきます。そのような状態で八時間労働をしなければなりません。
23 食べることができずに病気になり、死にかかっている人にとって、御飯は救世主です。一握りの御飯は、この世の一軒の家と取り替えても余りあるのです。ですから、御飯を食べている途中で息絶えると、その人の口にある御飯を取り出して食べるほどになります。狂気の沙汰といっても、そのような狂気の沙汰はありません。食べている御飯の中に石があって吐き出したものに御飯が一粒付いていれば、他の人がその石に付いた一粒を拾って食べるのです。生き地獄です。
そうしながら、反動分子を音もなく除去するのです。千人いたら、死んで監獄の後門から出ていく人が、一年で四百人近くになります。三年から四年もすれば、すべて死ぬということです。脂気がすべて抜けて死ぬまで仕事をさせるために、そのような政策を取るのです。無慈悲という程度ではありません。無慈悲なことにも、ある程度の限度があります。冷酷なことにも限度があるというのです。これは、限度をはるかに超えたことです。
24 私が興南の監獄に入っている時、千人近くの人がいました。その千人の中で、一年だけ過ぎると、四〇パーセントほどが死んで出ていきます。ですから、毎日葬式を行うのです。毎日、後門から棺が出ていくのを見なければなりません。自分の部屋にいる人たちも、そのように死んでいくのです。三十人いれば、十人以上死ぬことになります。
看護する人がいて、御飯を食べて死んでいくのではありません。病気になって苦しむことよりも、おなかがすく苦痛のほうが上回っているのです。病気になった人でも、仕事をしなければ御飯は半分しかもらえません。監獄で大きな一握りの御飯をもらうのと、半分をもらうのを比較してみると、大きいのをもらう時は天国のようで、小さいのをもらう時は地獄のようです。いくら話しても、皆さんには理解できないでしょう。
結局、仕事に出掛けて帰ってきて、やっと御飯がもらえるので、病気でも仕事をするのです。門を出る時に座り込んでいたとしても、這ってでも仕事に出掛けます。仕事をするふりでもしなければなりません。もう半分の御飯のために、あがきながら、仕事が終わるまで我慢するのです。帰って御飯をもう半分もらうことが、最高の理想だというのです。
ですから、御飯をもらう時間には、具合の悪い人はいません。自分のノルマに相当する御飯は、すべてしっかり食べるのです。そのように御飯をもらって戻り、死に物狂いでその御飯を食べている途中で、結局スプーンを落とし、目を閉じて死んでいく人が一人や二人ではありませんでした。
25 今でもお父様が一番忘れられないことがあります。私が興南の監獄にいるとき、母が一ヵ月に一回、面会に来ながら持ってきてくれたはったい粉を、監房にいる囚人たちと分け合って食べました。一つの監房に三十人以上いたので、たくさん分けてあげることはできず、新聞紙の切れ端に一さじずつ盛って、分けてあげたのです。
それは、牛カルビなど問題になりません。そこでの豆一粒は、外の世界での大きい雄牛十頭に勝るのです。いくら体面をつくろって威信をかざしたてる人でも、一粒の豆が落ちれば手を伸ばすようになっています。三十以上が一斉に手を伸ばし、互いに豆を拾おうとするのです。恐らく皆さんは,そのような境地を想象することもできないでしょう。
26 監獄にいる時、はったい粉を分けてあげる日は、正に祝宴の日です。お父様は、それをあげるのが惜しいからといって一人では食べません。絶対に一人では食べないのです。このはったい粉を水でこねて、はったい粉餅を作り、新聞紙に包んで作業場に持って出掛けます。食べたいのを我慢して、昼食の時間まで耐えなければならないのですが、その食べたい思いがどれほど切実か分かりません。それでも、それを分け合って食べたいので我慢するのです。汗を流して仕事をしながらも、一日中、そのことしか考えません。そうこうするうちに、昼食の時間になれば、それを分けて食べるのです。
私たちが働いていた肥料工場は大きいので、第一作業場と第二作業場に分かれていて、大きな肥料の山がそれぞれいくつかあります。作業時間にはそこで仕事をしますが、休み時間の十五分間は、それこそ天国です。その世界の生活というものは、体験してみたことがない人には分かりません。このような体験は、億万のお金とも交換することができません。それは血の涙で染まっているからです。自分の生涯のすべてを投入しなければならない世界が、正にその世界です。
27 監獄にいると、みな、おなかがすいて死にそうになります。肝油はどれほど生臭いでしょうか。その生臭い肝油に御飯を混ぜて食べても、生臭さが感じられないのです。それをコップに一杯そのまま注いで飲んでも、生臭くありません。それだけ体に脂気が不足しているということです。それがどれほど芳しいか分かりません。それだけ飢えているのです。ですから、(普通の人なら)仕事をしていても御飯が恋しく、自分が死ぬことも知らずに、ただ御飯ゆえに苦労して働くのです。働かなければ御飯を半分しかくれませんでした。御飯を半分しかもらえないというのは、死ぬほどつらいことです。そのような世界で彼らを慰労してあげ、彼らを教育してあげなければなりません。
私はたくさんの人を生かしました。「この工場で働けば、何ヵ月間はこのような症状が起き、また、このような症状も起きる。何ヵ月間はこれこれこのようになるが、この峠を越えられなければ必ず死ぬことになる。だから私の言うことを聞きなさい」と話し、大勢の人がお父様の言葉どおりに生活したおかげで、死にゆく環境の中で生き残りました。その人たちが弟子になったのです。ですから、監獄に行っても、教えてあげなければなりません。
28 興南の監獄にいる時、人々は御飯が恋しいので、どんなに具合が悪くても仕事に出掛けます。そうして帰ってきては、御飯をもらって三さじも食べられないまま、口に入れてかみながら死んでいく人もいます。すると、周りにいた人たち同土でけんかが起こります。口に入っていた御飯粒までも取り出して食べるのです。
お父様はそのような中でも、二、三週間も(御飯の)半分を人に分け与え、半分だけを食べて生きました。三年ではなく、五年、十年でも生きるのです。自然の中には目に見えない波長があります。自然が私を生かすために何かをあげたいと思うのです。私が自然を好むからです。近くの丘にりんご畑があれば、そのりんご畑から香りが漂ってきます。その香りをりんごのように感じて、ごくりとのみ込めば、本物のりんごを食べるのと同じなのです。
29 お父様は、りんご一つを握り締めて本当に感謝したことがあります。共産圏の監獄にいた時のことです。一年に二回、五月一日と一月一日には果物をくれます。りんごが一つ配給されるのですが、自分で良い物を選ぶのではなく、順番に分けてくれるのをもらうのです。虫食いの物でも、どんな物でも、ただ配給してくれる物を受け取らなければなりません。りんごを分けてもらうと、普通の人たちは受け取るなりむしゃむしゃと、一分もかからずにすべて食べてしまいます。
しかし、お父様は、「この色は、どれほどきれいなのだろう!この色を味わおう」と考えました。そして、「色を味わい、それから味を味わってみよう」と考えました。そうすると、口を開けて食べようという思いが湧かないのです。食ベずに取っておいてこそ、目の保養にもなり、匂いも嗅いだりできるので、食べようという思いをもつ自分になれないことを感じました。
かといって、それを持って行き来するような状況でもあません。ですから、食べることは食べるのですが、食べる時は、神様のみ前に祈りながら、「りんごを食べますが、私が世界で最初にこのような思いをもって食べます」という自負心をもって食べたことがありました。
30 お父様は、監獄で御飯をもらっても、「おかずがない」と不満を言うことはありませんでした。水を置き、おかずのない御飯を食べても、天の父を呼びつつ「あすの希望をもって歩んできたお前ではなかったか」と言って食べました。そこでは、おかずがあったとしても御飯と一緒に食べることはできません。
監獄の中は、食事をする人が千人近くいるので、お汁と御飯を一緒に与えることはできません。一時間以内に御飯を食ベなければなりませんが、お汁は向こうで、御飯はこつちでと、別々にくれるので混雑するのです。御飯だけ受け取るのに三十分かかります。そのように御飯とお汁を受け取っていれば、食事の時間が過ぎてしまいます。また、食事の時間が終わるやいなや、三分以内に作業場に出発しなければなりません。ですから、一方の手にお汁を受け取り、もう片方の手に御飯を受け取ってこのようにそろえて食べる余裕がありません。手当たり次第に、お汁はお汁で、御飯は御飯で列に並び、受け取ってすぐに食べるのです。御飯を先にもらえば御飯から食べます。おかずなしの御飯を食べるのです。
そこで、おかずなしで御飯を食べる方法を学びました。御飯だけでも本当においしいのです。私は昔から、おこげがとても好きです。神様はよくぞ私を訓練してくださったと思います。昔、私が食べたおこげの味が、その御飯の味です。そこにこげた味が少し加われば、普通の御飯には見向きもしなくなるほどおいしくなります。いつもそのように、お汁はお汁だけで、御飯は御飯だけで食べました。そのような場でも、私はみ旨を中心として生命を捧げる覚悟をし、神様のために孝の道理、忠の道理を尽くすのだと思って生活しました。