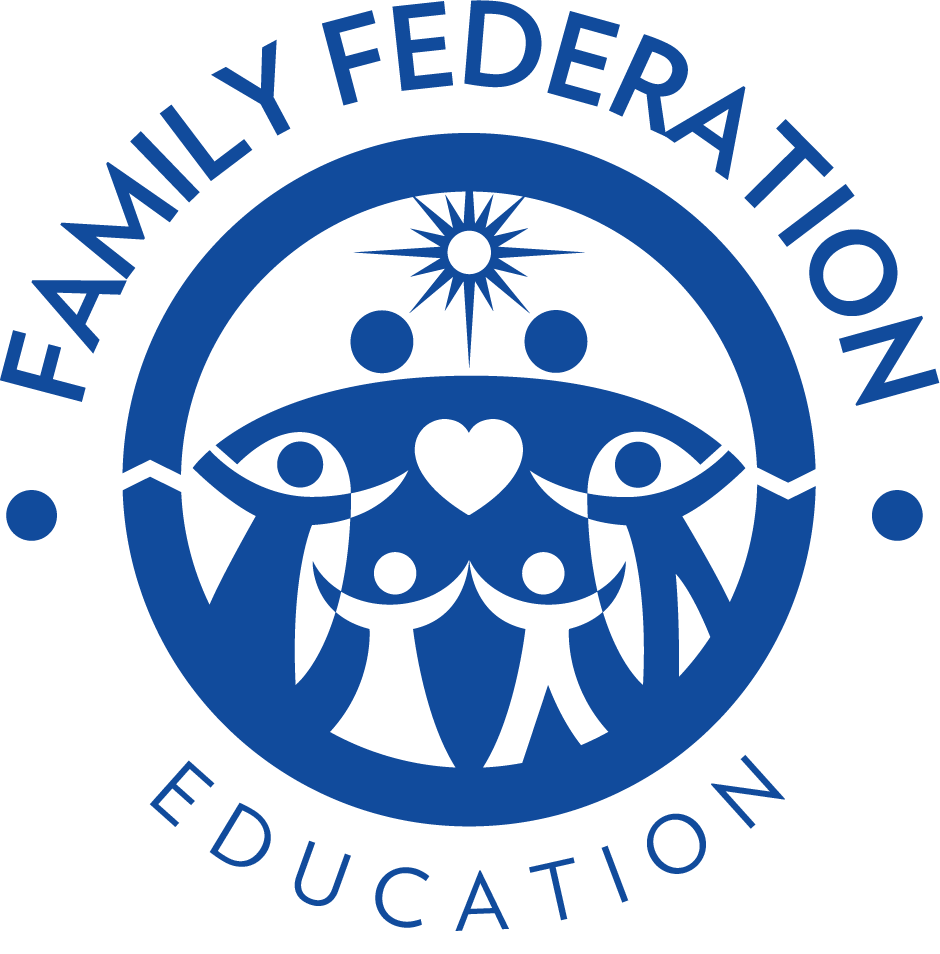平和を愛する世界人として 第10話
第二章 涙で満たした心の川―神の召命と艱難
恐れと感激が交差する中で
私は物心がついてくると、「将来何になるのか?」という問題について熱心に考え始めました。自然を観察し研究することが好きだったので、科学者になろうかと考えましたが、日本の収奪に苦しめられ、日に三度の食事さえままならない人たちの惨めな有様を目にして、考えを変えました。科学者になってノーベル賞を取ったとしても、ぼろを身にまとい、飢えた人たちの涙をぬぐい去ることはできないと思ったからです。
私は人々の流れる涙をぬぐい、心の底に積もった悲しみを吹き払う人になりたかったのです。森の中に横になって鳥たちの歌声を聞くと、「あのさえずりみたいに、誰もが仲良く暮らせる世の中を築こう。一人一人の顔をかぐわしい花のように素晴らしくしてあげたい」という思いが自然と沸き上がってきました。一体どんな人になればそうできるのか、それはまだよく分かりませんでしたが、人々に幸福をもたらす者になろうという心だけは固まっていきました。
私が十歳の頃、牧師である潤國大叔父の影響で、私たち一家は全員キリスト教に改宗しました。次姉と兄の精神的な病が按手祈疇を通して治癒したことから、猫頭山(標高三一〇メートル)のふもとにある徳興長老教会に入教し、熱心に信仰生活をしたのです。その時から、私は真面目に教会に通って、礼拝を]度も欠かしませんでした。礼拝時間に少しでも遅れると、あまりにも恥ずかしくて顔を上げることができませんでした。まだ子供なのに何を思ってそうしたかというと、私の心の中には、その時すでに神の存在がとても大きな位置を占めていたのです。そして、生と死や人生の苦しみと悲しみについて、深刻に悩む時間が増えていきました。
十二歳の時、曾祖父のお墓を移葬するのを見たことがあります。本来は一族の大人だけが参列する場でしたが、人が死ねばどうなるのか直接見たいという欲求に駆られて、必死に割り込んで入れてもらいました。墓を掘り起こして移葬する様子を見守った私は、驚きと恐怖に襲われました。儀礼作法を弁えた大人たちが集まって墳墓を開けた時、私の目に飛び込んできたのはか細い骨の欠片だけでした。両親から聞いていた曾祖父の姿は跡形もなく、白い骨だけがぞっとするような醜い姿を現しました。
曾祖父の骨を見てから、私はしばらくの間、その衝撃から抜け出すことができませんでした。「曾祖父も生きておられた時はみんなと全く同じ姿をしていたはずなのに……。そうすると、父や母も亡くなれば曾祖父のように白い骨だけが残るのか。自分も死ねばそうなるのか。人はみんな死ぬけれど、死んだ後は何も考えられず、そのまま横たわってばかりいるのか。思いはどこにいくのか……」
そうした疑問が、頭の中を離れませんでした。
その頃、家の中でおかしな出来事がたくさん起きました。今もはっきりと思い出すことが一つあります。礼装を仕立てようと、機織りで作る反物の出来上がったところまでを甕に入れておいたのに、ある晩、その白い布地が上の村の古い栗の木に掛かっていました。できた部分は一疋(二反)ほどの量になるまで少しずつ集めておいて、その木綿の生地で子供らの婚礼衣装を縫うのですが、これを故郷では「礼装」と呼びました。ところで、誰が夜中に家から遠く離れた栗の木に掛けたのか、それが分かりませんでした。到底人の仕業とは思えないので、近所の誰もが恐れたのです。
十五歳の頃、十三人の兄弟姉妹のうち五人の弟妹が、わずか一年で相次いでこの世を去るという悲劇も経験しました。一度に五人もの子供を失った両親の傷ついた心は言葉で表現しようがありません。ところが、ぞっとすることに、不幸はわが家の塀を越えて一族にまで及びました。丈夫だった牛が急に死に、続いて馬が死に、一晩のうちに豚が七匹も死んでいきました。
家族の苦難は民族の苦痛、世界の苦痛と無縁ではありません。次第にひどくなる日本の圧政とわが民族の悲惨な立場を見つめて、私の苦悩もただ深まるばかりでした。食べる物がなくて、人々は草や木の皮もあるだけもぎ取って、それを煮て食べるほどでした。世界的にも戦争が絶えませんでした。
そんなある日のことです。新聞で、私と同じ年の中学生が自殺したという記事を読みました。
「その少年はなぜ死んだのだろう。幼い年で何がそんなにつらかったのか……」
少年の悲しみがまるで私自身の悲しみであるかのよう感じられて、胸が締めつけられました。新聞を広げたまま三日三晩泣き通しました。とめどなく涙が流れて、どうしようもありませんでした。
世の中でなぜこれほど異様なことが相次いで起こるのか、なぜ善良な人を悲しみが襲うのか、私には全く理解できませんでした。曾祖父の墓を移葬する際に遺骨を目撃してからというもの、生と死の問題に疑問を持つようになった上、家の中で起こる理解しがたい出来事によって、私は宗教に頼るようになりました。しかしながら、教会で聞くみ言だけでは、生と死に関する疑問をすっきりと解くことができません。もどかしく思った私は、自然と祈りに没頭するようになりました。
「私は誰なのか。どこから来たのか。人生の目的は何か」
「人は死ねばどうなるのか。霊魂の世界は果たしてある のか」
「神は確実に存在するのか。神は本当に全能のお方なのか」
「神が全能のお方であるとすれば、なぜ世の中の悲しみをそのまま見捨てておかれるのか」
「神がこの世をつくられたとすれば、この世の苦しみも神がつくられたものなのか」
「日本に国を奪われたわが国の悲劇はいつ終わるのか」
「わが民族が受ける苦痛の意味は何なのか」
「なぜ人間は互いに憎み合い、争って、戦争を起こすのか」
等々、実に深刻で本質的な問い掛けが私の心を埋め尽くしました。
誰も容易に答えられない問いなので、答えを得るには祈るしかありません。私を苦しめる心の問題を神様に打ち明けてお祈りしていると、苦しみも悲しみも消えていって、心が楽になります。祈る時間は次第に長くなりました。祈りで夜を明かす日も、一日また一日と増えていきました。そしてとうとう、神様が私の祈りに答えてくださる日がやって来ました。それは何物にも代えがたい貴重な体験で、その日は、私の生涯に最も大切な記憶として残る、夢にも忘れることのできない一日です。
十五歳になった年の復活節(イースター)を迎える週でした。その日も、いつもと同じように近くの猫頭山に登って、夜を徹して祈りながら、神様に涙ですがりつきました。なにゆえこのように悲しみと絶望に満ちた世界をつくられたのか、全知全能の神がなぜこの世界を痛みの中に放置しておられるのか、悲惨な祖国のために私は何をしなければならないのか。私は涙を流して何度も何度も神様に尋ねました。
祈りでずっと夜を過ごした後、明け方になって、イエス様が私の前に現れました。風のように忽然と現れたイエス様は、「苦しんでいる人類のゆえに、神様はあまりにも悲しんでおられます。地上で天の御旨に対する特別な使命を果たしなさい」と語られたのです。
その日、私は悲しい顔のイエス様をはっきりと見、その声をはっきりと聞きました。イエス様が現れた時、私の体はヤマナラシの木が震えるように激しく震えました。その場で今すぐ死んでしまうのではないかと思われるほどの恐れ、そして胸が張り裂けるような感激が一度に襲いました。イエス様は、私がやるべきことをはっきりとお話しになりました。苦しんでいる人類を救い、神様を喜ぶようにしてさしあげなさい、という驚くべきみ言でした。
「私にはできません。どうやってそれをするのでしょうか。そんなにも重大な任務を私に下されるのですか」
本当に恐ろしくてたまらず、何とか辞退しようとして、私はイエス様の服の裾をつかんで泣き続けました。