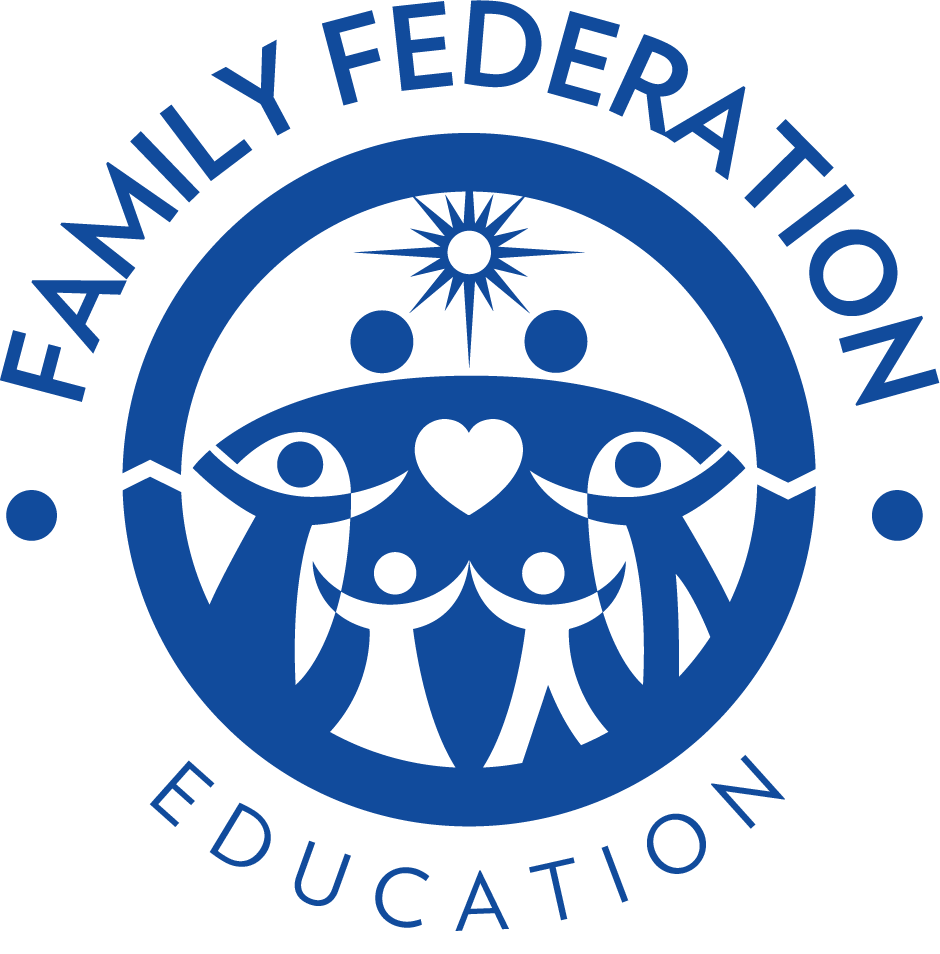平和を愛する世界人として 第22話
「あなだは私の人生の師です」
臨津江を渡ってソウル、原州、慶州を経て釜山に到着した日が一九五一年一月二十七日でした。釜山の地は避難民でごった返していました。朝鮮八道 (全土) の人が全部集まったかと思えるほどで、人が生活できる所は軒先までぎっしりと詰まっていて、お尻一つ入り込める隙間も残っていませんでした。仕方なく、夜は林の中に入って木の上で眠り、昼になるとご飯を求めて市内に下りていきました。
監獄で剃った頭はむくんでいました。内側を布団綿で継ぎ当てしたパジチョゴリ(男性用の韓服)はぼろぼろになり、染み付いた脂垢のせいで、雨に濡れると服の上を雨粒がころころと転がりました。靴も上の部分はくっついているだけ、下底はほとんど残っておらず、裸足で歩くのと同じでした。どこから見てもどん底の中のどん底、乞食の中の乞食です。働き口も所持金もなく、食べ物を得るには物乞いするしかないという惨な有様でした。
しかし、乞食をして回るときも、私はいつも堂々としていました。目ざといので、ぱっと見てご飯をくれそうにないと思うと、「われわれのように困った人を助けてこそ後で福を受けるのだ!」と言って、むしろ強気の態度でご飯をもらいました。そうやって手に入れたご飯を、日当たりの良い所に座って、数十人でぐるりと囲んで食べました。無一物で乞食の境遇にありながらも、お互い不思議と気持ちが通じ合うところがありました。
「おお、これは一体何年ぶりか?」
誰かが弾んだ声で呼ぶので振り返ってみると、日本留学時代に私の歌声に魅了されて友人となった厳徳紋でした。今は、世宗文化会館やロッテホテルなどを設計して、わが国有数の建築家になった人です。彼はみすぼらしい姿の私をぱっと抱きかかえると、有無を言わせず自分の家に連れていきました。
「行こう。さあ、わが家に行こう」
結婚していた彼は、一間の部屋に住んでいました。狭い部屋の真ん中に布団包みを吊して部屋を二つに分けると、彼は妻と幼い二人の子供を向こう側に行かせ、「さあ、あれからどうやって生きてきたのか話してくれ。どこでどうしているのかずっと気がかりだった。前は普通の親しい友人のようにしていたが、いつも君のことを友人以上の存在と思ってきた。心の中で一目も二目も置いていたことは知っていただろう?」と言うのでした。
私はその時まで、友人に自分の正直な心の内を明かしたことはありません。留学していた時、『聖書』を読んでいても友人が来ればすぐに片付けてしまうほど、自分の内面を見せませんでした。厳徳紋の家で初めて洗いざらい話したのです。
話は一夜で終わりませんでした。神と出会って新しく悟ったこと、三八度線を越えて平壌に行き布教活動を始めたこと、興南監獄を生き延びたこと。全部話すのに三日三晩かかりました。話をすっかり聞き終えると、厳徳紋はその場ですっくと立ち上がって、私に丁寧なお辞儀をしました。
「おい、それはどういうことだ?」
その手をつかんで引っ張りましたが、彼は頑として動きませんでした。
「これからは、あなたが私の人生の師です。このお辞儀は私が師に捧げる挨拶だから受け取ってください」
それから後、厳徳紋は私の生涯の友であり、同時に弟子として、私をそばから見守ってくれました。
厳徳紋の一間の部屋を出てから、釜山の第四埠頭で夜間の重労働に就きました。仕事が済んで労賃を受け取ると、草梁駅で小豆粥を買って食べました。熱い小豆粥は、冷めないように、器はどれもこれもぼろ布でしっかりと包んであります。私は小豆粥を一つ買って食べながら、その器を一時間も抱きかかえていました。そうすると、埠頭で夜通し働いてかちかちに凍りついた体がとろりと解けたのです。
その頃、草梁の労務者用の宿所に入ることができました。部屋が呆れるほど小さくて、対角線で横になっても壁に足が当たります。その後、知り合いの家に泊めてもらい、その部屋で鉛筆を削り、心を尽くして『原理原本』の草稿を書きました。極貧の生活だろうと何の問題もありませんでした。たとえゴミの山の中で暮らしたとしても、意思さえあればできないことはないのです。
二十歳を過ぎた金元弼も、仕事は何でもやりました。食堂の従業員として働いた時は、お焦げの残飯を持ち帰って一緒に煮て食べたりしました。また、画才を生かして、米軍基地に就職して絵を描く仕事もしました。
そうした中、凡一洞のボムネッコルに上がって小屋を建てました。ボムネッコルは共同墓地の近所なので、岩と谷間以外に何もない所です。谷間の上にも何もありません。斜めの崖で、そもそも自分の土地だと言えるような場所さえないので、まず斜面を水平に削って、その場所を固めて小屋の敷地を造りました。金元弼と共に石を割り、土を掘って、砂利にして運びました。土と藁を混ぜて作った壁石で壁を積み、米軍部隊からもらったレーション箱(兵士の野戦食であるレーションを詰めた箱)の底を抜いて平らにして、屋根に被せて出来上がりです。部屋の床には黒のビニールを敷きました。
バラックでも、これほどのバラックはありませんでした。岩場に建てた家なので、部屋の真ん中に岩がぷくっと突き出ていました。その岩の後ろ側に置いた座り机と金元弼の画架が調度品のすべてでした。雨が降れば部屋の中で泉が噴き出します。座った場所のすぐそばで、水がちょろちょろと音を立てて流れていく、とてもロマンチックな部屋でした。雨漏りがし、水が流れる冷え冷えとした部屋で寝ると、起きたときに鼻水がたくさん出ます。そうであっても、わずか一坪でもそうやって安心して横になれる場所があるという事実が、限りなく幸せに思えました。神の御旨に向かって行く道でしたから、劣悪な環境の中でも胸には希望があふれていました。
金元弼が米軍基地に出勤するとき、私は山の下まで付いていき、夕方仕事を終えて戻ってくるときは迎えに出ます。それ以外の時間は眠らずに鉛筆を削り、机に座って『原理原本』を書きました。米の甕に米はなくても、部屋に鉛筆はいっぱいありました。金元弼は、私が執筆に専念できるように、横にいて物心両面から私を助けてくれました。一日中働いてきて疲れているはずなのに、「先生、先生!」と言っては私に付いて回ります。もともと寝不足な私が便所でよく眠ることを知ってからは、便所まで付いてくるほどでした。それだけではありません。
「先生が本をお書きになるのを、少しでもお手伝いさせてください」と言って、私の鉛筆代を稼ぐために、新しい仕事まで始めたのです。それが米軍兵士の注文に応じて肖像画を描く仕事でした。当時、米軍兵士の間では、故国に帰る前に妻や愛人の肖像画を描いておくことが流行していました。図画用紙ぐらいの大きさの画布に糊を塗って、木の枠に付けて絵を描きます。売値は一枚四ドルでした。
金元弼のそのような真心がありがたくて、彼が絵を描くときは、私も横にいて黙々と助けました。彼が米軍基地に仕事に出かけると、画布にぱりっと糊を含ませ、木を切って枠を作ります。退勤してくるまでに、筆をすべて洗い、必要な絵の具を買っておきました。そうしてお枚か二枚だけだったのが、いつの間にか有名になって、寝る間も惜しんで二十枚、三十枚と描きました。
仕事が増えるにつれて、それまで手伝いだけしていた私も、直接絵筆を執って彼を助けるようになりました。元弼が顔の輪郭を大まかに描いて、私が唇や服の色を塗るというように、共同して仕上げるのです。
一緒に儲けたお金は、鉛筆と絵の道具を買うことを除いては、すべて教会のために使いました。神のみ言を文章にまとめることも重要ですが、もっと多くの人に神の御旨を知らせることが急がれていました。